ミッション・沿革
ミッション
研究関連プロジェクト/教育開発関連プロジェクト/交流・連携関連プロジェクト
当センターでは、教養のための基盤研究と成果公開を掲げています。教養のための研究を推進するのは、先に示したように、教養に関する明確な知見は未だ得られていないという現状認識からです。但し、教養の研究、教育の実践、方法論の探求は、ヒエラルキーをもったピラミッド状のものではなく、互いが透けてみえるパランプセストのような重層的なイメージで考えています。たとえば、研究が、教育に反映されたり、方法論を導き出すことを期待していますし、また、教育が、研究の対象になったり、方法論の効果を証明することもあるでしょう。さらに、方法論そのものが、研究し、教えられるべき教養の一つの形になるかもしれません。当センターでは、研究と教育と方法論の探求を並行して進めていきたいと思っています。そして、それこそが学問の形であり、大学のあり方であると考えています。
■研究関連プロジェクト
「教養」の本質を⾒極め、それを実践するための教養教育を考究し、その研究成果を発信し続けます。
慶應義塾⼤学教養研究センターは(1)学問の発展、(2)教養教育、(3)⾼度専⾨職教育、(4)健全な学⽣⽣活の四つが⼤学の使命を果たすために必須であると考えています。この四つは、⼤学という場において相互に関連し重なるものですが、当センターは、「教養」の多様な役割について特に⼤きな関⼼を持ち、探究しています。社会の先導者たらんとするものは、「教養」を⼟台にして、学問的にも⼈間的にも広い視野にたって、先端的研究を⾏わなければなりません。それなくしては、いくら⾼度な技術を⾝につけようと真にそれが⼈類にとって有効に活かされることはないからです。
■教育開発関連プロジェクト
「学部・学科の壁にとらわれない独⾃の内容による授業を開講し、教養教育の発展に寄与します。
教養教育についての研究を重ね、実験授業を経て寄附講座へと発展した授業を多数開講しています。
■交流・連携関連プロジェクト
教養の最⼤の特徴は「つなぐ⼒」です。「交流と連携」は、教養の本質的性格です。
教養は、過去に⼈類が研究し、思索し、創造することで遺してくれた財産を、現代の私たちが受容する⼒を与えてくれます。また、教養は、異なる環境で育ってきた⼈間同⼠がお互いに思想を交換し、それを磨き合う機会を与えてくれます。交流と連携は、私たちが教養を⾝につける⼿段であるとともに、教養の⽬標でもあります。
沿革
| 2002年5月 | 新入生歓迎行事「第1回日吉能 清経」(シテ 坂井音重) |
|---|---|
| 2002年7月 | 慶應義塾大学教養研究センター開所、羽田功所長就任
教養教育に関するアンケート企画・実施 |
| 2002年9月 | 開所記念シンポジウム「教養教育をめぐって」 |
| 2002年10月 | 極東証券寄附公開講座「『教養』とは何か―よりよく生きるために―(全10回) |
| 2002年12月 | 文部科学省学術フロンティア推進事業「表象文化に関する融合研究」プロジェクト、教養研究センター事業に移管(2000年度採択~2004年度まで) |
| 2003年4月 | 「表象文化に関する融合研究」プロジェクト中間発表パネル展示 |
| 2003年6月 | HAPP企画舞踏公演「野の婚礼―新しき友へ」 |
| 2003年7月 | シンポジウム「自然科学系を核とした教養教育の将来」 |
| 2003年10月 | 極東証券寄附公開講座「生命の魅惑と恐怖―生命にまつわる多彩な知をめぐって」
連続セミナー「FDを考える」(~2007年3月まで全7回) 実験授業「スタディ・スキルズ」開講 |
| 2003年11月 | シンポジウム「身体知を核とした教養教育の将来」 |
| 2003年12月 | HAPP企画「塾長と日吉の森を歩こう」(現在に至る)
シンポジウム「開かれ行くキャンパス1 国際学生懇談会in Hiyoshi」開催 |
| 2004年3月 | 教養研究センター選書発刊開始(現在に至る) |
| 2004年4月 | 「スタディ・スキルズⅠⅡ」正規授業化 |
| 2004年9月 | 生命の教養学 正規授業化「ぼくらはみんな進化する?―脳・性・免疫・科学と社会」 |
| 2004年10月 | 横山千晶所長就任
「横浜市民大学講座」を「日吉キャンパス公開講座」に改称、「21世紀と私たち―思想・身体・表象・環境・社会・民族」(~12月、全10回) |
| 2004年11月 | 「表象文化に関する融合研究」プロジェクト最終報告会 |
| 2005年1月 | 韓国教育研究機関訪問
特定研究 文部科学省・学術フロンティア「超表象デジタル研究」プロジェクト別報告会 |
| 2005年2月 | スタディ・スキルズ プレゼンテーション・コンペティション |
| 2005年3月 | 特定研究 文部科学省・学術フロンティア「超表象デジタル研究」最終報告パネル展示会
「表象文化に関する融合研究」報告書発行(全7巻) |
| 2005年4月 | 生命の教養学「生命と自己―今、“自分”が、“生きている”、とは?」
「スタディ・スキルズⅠⅡ」を「アカデミック・スキルズⅠⅡ」に改称(現在に至る) |
| 2005年5月 | 基盤研究「慶應義塾大学の教育カリキュラム研究」発足(~2009年3月まで)
基盤研究「身体知プロジェクト」発足(~2010年3月まで) |
| 2005年7月 | 遠山敦子元文部科学大臣・安西祐一郎塾長特別公開対談「教養教育の将来を見据えて―次世代に何をどう伝えるか」 |
| 2005年9月 | 文部科学省学術フロンティア推進事業「超表象デジタル研究」プロジェクト採択(~2007年度まで) |
| 2005年10月 | 日吉キャンパス公開講座「創作とメディア」(~12月、全10回) |
| 2006年2月 | 「スタディ・スキルズ プレゼンテーション・コンペティション」を「アカデミック・スキルズ プレゼンテーション・コンペティション」に改称、開催(現在に至る) |
| 2006年3月 | 『慶應義塾大学の教育カリキュラム研究―改革への処方箋』発行 | 2006年4月 | 生命の教養学「生命を見る・観る・診る」 | 2006年6月 | 公開セミナー「ミシェル・フーコー使用法」 |
| 2006年9月 | 実験授業「体をひらく、心をひらく」
「三田の家」開設(~2013年10月) 日吉キャンパス公開講座「自然と科学と人間」(~12月、全10回) |
| 2006年10月 | 『アカデミック・スキルズ―大学生のための知的技法入門』刊行
「クリスト&ジャンヌ=クロード」公開講演会 |
| 2006年12月 | 「新しい教養教育の支援」事業成果報告会 |
| 2007年4月 | 基盤研究「身体知プロジェクト」声プロジェクト発足
未来先導基金「『声』を考える―教育現場での実践とその意義」採択 生命の教養学「誕生と死―その間にいる君たちへ」 |
| 2007年6月 | 基盤研究「慶應義塾大学の教育カリキュラム研究―改革への処方箋―」シンポジウム
教員サポート第1回「メディア・リテラシ・ワークショップ」 公開講座「サイエンス・カフェ」開講(~2012年度まで。2013年度より自然科学研究教育センターへ移管) |
| 2007年8月 | 「身体知」の実験授業および「身体知・音楽」の授業実践
実験授業「文学・チャタレー夫人の恋人」 |
| 2007年9月 | 日吉キャンパス公開講座「モノを創る」(~12月、全10回) |
| 2007年11月 | 実験授業「アートで体をひらく、心をひらく」 |
| 2008年1月 | 教員サポート「発達障害を抱える学生への関わり方」 |
| 2008年2月 | センター活動報告会(内部評価)「活動を振り返って―教養研究センター5歳7ヶ月」 |
| 2008年3月 | センター活動報告会(外部評価)「みいだす、つなげる、ひろげる―教養研究センターの過去・現在・未来」
「超表象デジタル研究」報告書発行・DVD制作 |
| 2008年4月 | 未来先導基金「『三田の家』 21世紀的学生街の創出に向けて」採択
生命の教養学「生き延びること―生死の後へ」 |
| 2008年5月 | 日吉キャンパス公開講座「モノを創る」(3講座各4回) |
| 2008年7月 | 実験授業「文学2:ジョン・ポールの夢を体験する」 |
| 2008年8月 | 鶴岡セミナー『鶴岡に学ぶ「生命」』―心と体と頭 |
| 2008年9月 | 日吉キャンパス公開講座「記録・記憶と構想の現場」( ~12月、全10回) |
| 2008年10月 | 実験授業「体をひらく、心をひらく―ボクってどこにいるの」 |
| 2008年11月 | 学び場プロジェクト「ピア・メンターによる学習相談アワー」(現在に至る) |
| 2008年12月 | 「三田の家」大学地域連携シンポジウム |
| 2009年1月 | 教員サポート「学生相談室の活動と連携」「発達障害を抱える学生への関わり方」 |
| 2009年3月 | 『慶應義塾大学の教育カリキュラム研究―4年間を見越した教養教育の研究』発行 |
| 2009年4月 | 生命の教養学「ゆとり」 |
| 2009年5月 | 日吉キャンパス公開講座「見て・感じて・動いて味わうシェイクスピア」(~6月、全4回)、「絵画を聞く、音楽を見る、自我の行方」(~6月、全4回)、「創造する自己」(~6月、全4回)、「メディア・リテラシー入門」(~6月、全4回)、「ゲーテの『ファウスト』第1部を読む」(~6月、全4回) |
| 2009年7月 | 教員サポート「メディア・サービス活用術」 |
| 2009年8月 | 「鶴岡セミナー」を「庄内セミナー」に改称、『庄内に学ぶ「生命」―心と体と頭と―』
実験授業「文学3:J.M.クッイェーの謝肉祭」 |
| 2009年9月 | 文部科学省「大学教育・学生支援推進事業」大学教育推進プログラム(教育GP)「身体知教育を通して行う教養言語力育成」採択(~2011年度まで)
日吉キャンパス公開講座「天からの文を読み解いてみよう―世界天文年に因んで」(~12月、全10回) |
| 2009年11月 | 基盤研究「慶應義塾大学の教育カリキュラム研究(2)―4年間を見越した教養教育の研究―」シンポジウム
教員サポート「少人数セミナーの指導法について」 |
| 2010年3月 | 教育GPプログラム GPシンポジウム「身体知と教養言語力育成」 |
| 2010年3月~4月 | 教育GP関連事業(全43)実施 |
| 2010年4月 | 「アカデミック・スキルズⅢ 批評と創作」(現在の「身体知・映像」) |
| 2010年5月 | 生命の教養学「『異形』をめぐる理系と文系の対話」
教員サポート「“学生の悩みについて悩み”を解消するために」 日吉キャンパス公開講座「実験で学ぶ気象の教室」(~6月、全4回)「自分の位置を正確に知る方法の決定版 GPSの原理と応用」(~6月、全2回) |
| 2010年6月 | 実験授業「エディティング・スキルズ」
日吉キャンパス公開講座「理系・文系・ダンス系―生きること、学ぶこと、働くこと」(~6月、全3回)、「体と頭でハムレット―演劇と映画」(全3回)、「バッハ~深遠なる魂の響き~を聴く」(~7月、全2回) |
| 2010年8月 | 「身体知―創造的コミュニケーションと言語力」正規授業化
庄内セミナー「芭蕉が見た庄内の生命」 |
| 2010年9月 | 実験授業「アートと文学―ワークショップ Alfred Tennyson,"The Lady of Shalott"の創造的解題:英語版創作をめざして」
日吉キャンパス公開講座「読むことの過去と未来」(~12月、全10回) |
| 2010年10月 | 不破有理所長就任
実験授業「心をひらく体をひらくー初心者のための瞑想入門-」 |
| 2011年1月 | 教員サポート「学生相談室から垣間見る昨今の慶應生の姿」 |
| 2011年2月 | 大学カリキュラムに関する教員アンケート実施 |
| 2011年3月 | 教育GP関連企画「身体知教育を通して行う教養言語力育成」中間報告会 |
| 2011年4月 | アカデミック・スキルズ(英語)開講
HAPP企画「蝋燭能 羽衣」(シテ 坂井音重) |
| 2011年5月 | 「研究の現場から」第1回(現在に至る)
生命の教養学「『共生』をめぐる理系と文系の対話」 実験授業「エディティング・スキルズ(製本教室)」 |
| 2011年6月 | 自由研究セミナー「アーサー王伝説解題から創作へ」
実験授業「文学-読書から朗読、そして創作へ」 |
| 2011年7月 | 教育カリキュラムシンポジウム「これでいいのか?日吉のカリキュラム」(2010年2月実施のアンケート結果に基づく)
社会・地域連携「大学教育と社会・地域連携のあり方を考える」セミナー |
| 2011年10月 | 日吉キャンパス公開講座「災害とメディア」(~12月、全8回)
社会・地域連携「なぜSFCから学生主導の地域連携プロジェクトが次々と生まれるか」セミナー |
| 2012年1月 | 文部科学省「大学教育・学生支援推進事業」【テーマA】大学教育推進プログラム「身体知教育を通して行う教養言語力育成」(教育GP)最終報告会および外部評価
教員サポート「社会で生きる力、人とつながること、遊ぶこと、学生相談室として」 社会・地域連携「大学教育と社会・地域連携のあり方を考える」セミナー |
| 2012年4月 | 未来先導基金「庄内セミナー」、「ヨコハマの『かどっこ』から考える日本と世界の未来」採択
「身体知・音楽ⅠⅡ」正規授業化 生命の教養学「成長」 |
| 2012年6月 | 「学びの連携」プロジェクト発足(現在に至る) 第1回公開セミナー
「学生の主体性を育む教育方法の探求―ケースメソッドの効果的運用の試案―」 開所10年記念企画「学生論文コンテスト」開催概要の発表(表彰式2013年2月5日) |
| 2012年8月 | 学びの連携「ケースメソッドを用いたクリティカル・リーディング」 |
| 2012年9月 | 学びの連携「ポストデザイン・ポストシステムの方法論によるイノベーションの新たな地平開拓
日吉キャンパス公開講座「東北の魅力再発見 日本ってなんだろう」(~11月、全8回) |
| 2012年10月 | 小柴昌俊博士講演会「宇宙、人間、素粒子」(共催、学会・ワークショップ等開催支援)
カリキュラム研究「東京大学の秋季入学構想をめぐって」 |
| 2012年11月 | 学びの連携「Alfred Lord Tennysonの詩 “ The Lady of Shalott”を読み、分析し、創作する」
開所10年記念企画「学びの旅のすゝめ:みちのく見聞録」(センター企画・JTB法人東京主催) |
| 2012年12月 | 日吉キャンパス公開講座【特別講座】「中国を見る目を養う―日吉キャンパスから考える日中国交正常化40年」 |
| 2013年1月 | 教員サポート「大学における発達障害を抱える学生へのサポート」 |
| 2013年3月 | 開所10年記念企画映像「はじめてのアカデミック・スキルズ―10分講義シリーズ―」(15本)制作・公開
カリキュラム研究「国際基督教大学の3学期制とカリキュラム」 学びの連携「塾生による塾生のための半学半教の場作り」 |
| 2013年4月 | 「アカデミック・スキルズⅢ―批評と創作」を「身体知・映像」に改称(現在に至る)
「情報の教養学」第1回講演会(現在に至る) 生命の教養学「新生」 |
| 2013年6月 | 基盤研究「慶應義塾大学の教育カリキュラム研究―学事日程と日吉キャンパス」シンポジウム |
| 2013年8月 | 庄内セミナー「庄内に学ぶ生命-あらためて生と死を考える」
学びの連携「学生の主体性を育む教育方法の探究」 |
| 2013年10月 | 日吉キャンパス公開講座「人の形―身体の表現と認識、身体の今とこれから」(~12月、全9回) |
| 2013年11月 | 実験授業「日吉学」開始(~2018年3月まで) |
| 2013年12月 | コレギウム・ムジクム・オペラプロジェクト《 コジ・ファン・トゥッテ》
日吉キャンパス公開講座【特別講座】「出版文化史の東西(日中交流400周年記念) |
| 2014年1月 | 教員サポート「学生相談室における心理的支援」 |
| 2014年4月 | 生命の教養学「性」 |
| 2014年7月 | 学びの連携「本の世界への探求法ワークショップ」 |
| 2014年8月 | 庄内セミナー「生きることを考える―庄内に学ぶ生命」 |
| 2014年10月 | 小菅隼人所長就任
教養研究センター監修『学生による学生のためのダメレポート脱出法』刊行 日吉キャンパス公開講座「言葉と想像の翼」(~12月、全8回) |
| 2014年11月 | 学びの連携「交渉力体験ワークショップ ハーバード×慶應流交渉学」 |
| 2015年1月 | 教員サポート「学生相談室における発達支援」
学びの連携「パターン・ランゲージ体験ワークショップ」 |
| 2015年3月 | リサ・バルデス ダートマス大学教授講演会「超一流リベラル・アーツカレッジの考え方」 |
| 2015年4月 | 生命の教養学「食べる」
実験授業「身体知・音楽(発展・声楽クラス)」(現在の「身体知・音楽ⅢⅣ」)開講 |
| 2015年8月 | 庄内セミナー「生きることの意味を問う」 |
| 2015年10月 | 教養研究センター監修『クリティカル・リーディング入門』刊行
日吉キャンパス公開講座「色と紋様の世界」(~12月、全8回) 神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア講座事業に採択、「文化としての病と老い」開講 |
| 2016年3月 | 神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア講座研究会 |
| 2016年4月 | 読書会推進企画「晴読雨読」(現在に至る)
生命の教養学「飼う」 「身体知・音楽ⅢⅣ」正規授業化 |
| 2016年8月 | 庄内セミナー「庄内に学ぶ<生命(いのち)>-心と体と頭と―」 |
| 2016年10月 | 日吉キャンパス公開講座「地方の力と『再生』」(~12月、全8回)
神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア講座事業に採択、「文化としての病と老い」開講 |
| 2016年12月 | コレギウム・ムジクム・オペラプロジェクト《ドン・ジョバンニ》 |
| 2017年2月 | 神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティアワークショップ |
| 2017年4月 | 生命の教養学「感染」 |
| 2017年5月 | 基盤研究 講演会no.1「『オイディプス王』を上演する―古典と教養」
教養研究プロジェクト開始(~2019年度まで) |
| 2017年8月 | 庄内セミナー「庄内に学ぶ<生命(いのち)>-心と体と頭と―」 |
| 2017年10月 | 基盤研究「教養研究」シンポジウムno.1「日本の近現代を“教養”から考える」
日吉キャンパス公開講座「観光と開発」(~12月、全8回) |
| 2017年12月 | 基盤研究 講演会no.2「教養と演劇:現代人にとって、演劇は教養になるか」 |
| 2018年4月 | センター主催 読書会4件開催
生命の教養学「組織としての生命」 |
| 2018年6月 | 基盤研究「教養研究」シンポジウムno.2「藝術と教養―藝術は教養たりえるのか?―」 |
| 2018年8月 | 庄内セミナー「庄内に学ぶ<生命(いのち)>-心と体と頭と―」 |
| 2018年9月 | 日吉キャンパス公開講座「ルールと作法」(~11月、全5回) |
| 2018年10月 | 基盤研究「教養研究」シンポジウムno.3「クラシック音楽を“教養”から考える」 |
| 2019年1月 | 基盤研究 講演会no.3「大地の芸術学―庭園と建築を歩む」 |
| 2019年2月 | 羽田功教授最終講義「異端の教養学」 |
| 2019年3月 | コレギウム・ムジクム カナダ、ブリティッシュ・コロンビア大学生との交流コンサート「ドイツ・バロックの音風景」(2018年度未来先導基金公募プログラム) |
| 2019年4月 | 基盤研究文理連接プロジェクト「医学史と生命科学論」「研究会の経済」
生命の教養学「生命の経済」 |
| 2019年7月 | 基盤研究 講演会no.4「教養」としての『百科全書』―共時性の中の文化と知識 |
| 2019年8月 | 庄内セミナー「庄内に学ぶ<生命(いのち)>-死から学ぶ生-」 |
| 2019年9月 | 実験授業「機械(マシン)と学ぶ『くずし字』(はじめの一歩)」
「日吉学」正規授業化 ⽇吉キャンパス公開講座「出⼝戦略とその先の未来」(~11月、全5回) |
| 2020年1月 | 基盤研究 講演会no.5「アート:見えないものを見る」 |
| 2020年2月 | 実験授業「マシンと読むくずし字―デジタル翻刻の未来像」シンポジウム |
| 2020年3月 | 「アカデミック・スキルズ―10分講義ビデオ―」新シリーズ(15本)制作・公開 |
| 2020年11月 | 「研究の現場から」第28回オンライン開催(現在に⾄る)
<選書刊⾏記念企画>著者と読む教養研究センター選書(現在に⾄る) |
| 2020年12月 | HAPP企画 新⼊⽣歓迎⾏事「笠井叡舞踏公演「⽇本国憲法を踊る」(無観客収録配信) |
| 2021年1月 | 庄内セミナー:特別講話(動画)公開 |
| 2021年3月 | 「アカデミック・スキルズ―10分講義シリーズ―」公開(9本)制作・公開 |
| 2021年4月 | 基盤研究⽂理連接プロジェクト「医学史と⽣命科学論」研究会を「基盤研究⽂理連接プロジェクト」に改称(現在に⾄る) |
| 2021年10月 | 実験授業「ゲーム学」開講
日吉キャンパス公開講座「⼆⼑流の豊かな世界」(~12月、全5回) |
| 2022年2月 | 武藤浩史教授最終講義「モダニズム⽂学のスピリチュアリティーズ」 |
| 2022年3月 | 「アカデミック・スキルズ―10分講義ビデオ―」新シリーズ(6本)制作・公開 |
| 2022年4月 | 読書会 晴読雨読 アメリカ文学の中の村上春樹、日本文学の中の村上春樹(~2023年5月) 生命の教養学「記憶」 |
| 2022年5月 | 実験授業「エンターテインメントビジネス論」開講 |
| 2022年6月 | HAPP企画「能の流儀―謡と仕舞―」(講師 坂井⾳雅、他) |
| 2022年7月 | 基盤研究 講演会no.6「西洋文明の源流としての旧約聖書-生きるための知恵を学ぶ-」 |
| 2022年8月 | 庄内セミナー「庄内に学ぶ<生命(いのち)>-今、あらためて死から生を考える-」 |
| 2022年9月 | ⽇吉キャンパス公開講座「舞台裏のストーリー」(~12月、全5回) |
| 2022年10月 | 片山杜秀所長就任
「ゲーム学」正規授業化 |
| 2022年11月 | 基盤研究 講演会no.7「キリスト教は『世界』をどう取り戻すか―救済宗教のakosmismを越えて」 |
| 2023年1月 | HAPP企画「国民文化のなかのタイ舞踊ー講演、実演、体験ー」 |
| 2023年2月 | 不破有理教授最終講義「アーサー王伝説に魅せられて~研究と教育と~」 |
| 2023年3月 | 「アカデミック・スキルズ―10分講義ビデオ―」新シリーズ(4本)制作・公開 |
| 2023年4月 | 「エンターテインメントビジネス論」正規授業化 情報の教養学「進化するAIと変わる著作権・肖像権」 生命の教養学「贈与」 |
| 2023年5月 | 【講演・ワークショップ】日吉キャンパスパヴィリオン誕生とこれから みなさんmiraiプロジェクト(~2026年3月) HAPP企画 鎌倉大仏の学際的調査と研究-鎌倉大仏と研究の「曼荼羅」 HAPP企画 新入生歓迎行事 上杉満代舞踏公演「命」 |
| 2023年6月 | 基盤研究 教養研究講演会 no.8「激動の流れを生きて」―ウクライナ戦争を念頭に、今ベトナム戦争を考える― HAPP企画 新入生歓迎行事 ポストコロナを彩るメイク術 読書会 晴読雨読「アイデアの系譜学」(~2026年3月) |
| 2023年7月 | 情報の教養学「独立自尊とAI」 |
| 2023年8月 | 創造力とコミュニティ研究会20「なぜ居場所は必要なのか~ボードゲームのある居場所~」 第12回「庄内セミナー」「庄内に学ぶ<生命(いのち)>-自然、戦争、信仰-」 |
| 2023年9月 | 創造力とコミュニティ研究会21「地域のアートNPOと、市民活動」 |
| 2023年10月 | 日吉学特別企画 キャンパスの戦争~日吉台地下壕見学会 情報の教養学「脳情報を光で取得する技術、脳情報を光で操作する技術」 基盤研究 教養研究講演会 no.9 キリスト教の源流-イエスとパウロ- 日吉キャンパス公開講座「人生100年に備える」(~12月、全5回) 【講演・ワークショップ】スリランカの仏教ナショナリズムとイスラームの聖地 【講演・ワークショップ】日吉電影節 2023-中国アニメの現在地- HAPP企画 「路上の⾝体祭典H!」新人H ソケリッサ |
| 2023年11月 | 【HAPP企画】新入生歓迎行事/教養の一貫教育Vol.7 Voix/Voie 詩と音楽の交差するところ3 情報の教養学「WISEなまちづくり」 【講演・ワークショップ】ウクライナについて学ぶ~ウクライナ語と文化基礎コース:Learn about UKRAINE~AN INTRODUCTION TO UKRAINIAN LANGUAGE AND CULTURE 教養の一貫教育「舞踏家・今貂子による身体ワークショップ「生きること 踊ること」 |
| 2023年12月 | 【講演・ワークショップ】慶應ウクライナ・セミナーPart II 「現代ウクライナとその文学」/Keio University Seminar on Ukrainian Language & Culture Part II “Contemporary Ukraine and its Literature” 情報の教養学「DX時代における人とコンピュータの関係性のデザイン」 |
| 2024年1月 | 創造力とコミュニティ研究会 22「若者たちの居場所」 |
| 2024年2月 | 【実験授業】「『アート思考』で学ぶオペラと美術」『20XX年の革命家になるには―スペキュラティヴ・デザインの授業』 【講演・ワークショップ】ウクライナ文化の挑戦-激動の時代を越えて |
| 2024年3月 | 【講演・ワークショップ】ろう者と聴者による多様性ワークショップ |
| 2024年4月 | 【講演・ワークショップ】Ageing & Literature Symposium 情報の教養学「今だからこそ学ぶプログラミングとアルゴリズム」 情報の教養学「人はなぜ、それを未来に残すのか~デジタルアーカイブの夢と、権利、法」 生命の教養学「死と再生」 【講演・ワークショップ】The Colour Revolution in Victorian Literature and Art ヴィクトリア朝文学・芸術の色彩革命 |
| 2024年5月 | HAPP企画 祭祀遺跡から古代の出雲、杵築大社の成立を考える -神と社の考古学- みなさんmiraiプロジェクト 公開シンポジウム① 南三陸発!慶應の森からひもとく生物多様性 HAPP企画 新入生歓迎行事 笠井叡ポスト舞踏公演『未完成』 HAPP企画 ライブラリーコンサート2024 HAPP企画 みなさんmiraiプロジェクト 公開シンポジウム➁ 今、地震がおきたら?―キャンパスで考える防災― 【講演・ワークショップ】Latin America since 1968: History and Historiography 【講演・ワークショップ】プロレス/ルチャ・リブレが映し出す ラテンアメリカと日本 |
| 2024年6月 | 情報の教養学「そもそも「情報」って何なんだろう?」 HAPP企画 慶應義塾大学古楽アカデミー・室内アンサンブル演奏会《バロック後期のドイツ室内楽作品》 【講演・ワークショップ】キャンパスにえがく夢:第5校舎跡地の未来 |
| 2024年7月 | 情報の教養学「AI時代の高等教育」 読書会 晴読雨読「アイデアの系譜学」第8回 スペシャル対談企画(片山杜秀×若澤佑典) 基盤研究 教養研究講演会 no.10 「宗教の中国化」政策:文化的レトリックと統治戦略 創造力とコミュニティ研究会 23「共に暮らす~ペットと私たち~」 |
| 2024年8月 | 創造力とコミュニティ研究会24「共に暮らす その2 鳥が期待する人との暮らし方~インコの心から紐解く~」 |
| 2024年9月 | 【講演・ワークショップ】フランス植民地教育史研究の実態と展望 ⽇吉キャンパス公開講座「際(きわ)」(~11月、全5回) 創造力とコミュニティ研究会25「植物が彩る暮らし 植物の力と染色」 HAPP企画 新入生歓迎行事 教養の一貫教育Vol.9 Voix/Voie 詩と音楽の交差するところⅣ 吉増剛造×高橋世織×マリリア 【講演・ワークショップ】第25回英詩研究会 |
| 2024年10月 | 情報の教養学「情報工学から想像学へ:ヒューマンエージェントインタラクションから物語応用までの系譜」 HAPP企画 古楽トークコンサート スペイン中世音楽の楽しみ 【講演・ワークショップ】スペイン史学会⼤会第45回⼤会 中近世イベリア半島におけるイスラーム観の変容 レコンキスタ期・ムデハル期・モリスコ期の比較検討 創造力とコミュニティ研究会26「社会課題をアートで解決するグローバルアートチーム LITTLE ARTISTS LEAGUEの全て」 |
| 2024年11月 | 創造力とコミュニティ研究会27「ヨコハマ喫茶去」 【講演・ワークショップ】ルーブリック作成と活用を考える ワークショップ&ディスカッション 【講演・ワークショップ】第19回 日本応用老年学会大会 「新世代シニアのための社会創造-産官学民が共創する未来ビジョン」公開シンポジウム HAPP企画 ライブラリーコンサート2024 Jazz 日吉図書館 Library Concert 2024 Fall HAPP企画 HAPPO STYROL INSTALLATION 教養の一貫教育Vol.10 舞踏家・上杉満代による舞踏ワークショップ「呼吸を遊び 体と遊び 床を踏む!」 実験授業 教養のための「金融リテラシー入門」開講(~12月、全4回) |
| 2024年12月 | HAPP企画 新入生歓迎行事 メイクで探求する個性~自分を引き立たせる技と心~ 情報の教養学「なぜAIは差別社会を作ってしまうのか?~問題と防止策について~」 HAPP企画 室内楽・ピアノマラソンコンサート、他 |
| 2025年1月 | 【講演・ワークショップ】INTERNATIONAL SYMPOSIUM RECEPTIONS OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITY IN JAPAN 【講演・ワークショップ】国際シンポジウム Japanese Cinema: What Is It? 創造力とコミュニティ研究会28「循環する生と死を考えるー巡る命に想いを寄せてー」 |
| 2025年2月 | 創造力とコミュニティ研究会29「ワークショップ 砂で描く、私の心」 |
| 2025年3月 | 【講演・ワークショップ】第26回英詩研究会 【講演・ワークショップ】The 6th International FrameNet Workshop 2025 (IFNW2025) Frames and Cognitively Grounded Language Resources in Linguistics and AI |
| 2025年4月 | 情報の教養学「わたしの声はわたしのもの?わたしの顔はわたしのもの?〜デジタルレプリカの法律学入門」 【講演・ワークショップ】鳥の詩学 HAPP企画 新入生歓迎行事 福澤諭吉と北里柴三郎―近代史上の慶應医学部― 【講演・ワークショップ】刊行記念ブックトーク「近代イギリスの動物史 歴史学のアニマル・ターン」 |
| 2025年5月 | 情報の教養学「TODによるサステナブルな田園都市」 【講演・ワークショップ】公開セミナー「現代ベトナムを知る」 HAPP企画 ライブラリーコンサート 2025 春 【講演・ワークショップ】フランスにおけるマグレブ系「移民」映画『シャアバの子供』上映会・作家アズーズ・ベガーグとの対談 HAPP企画 新入生歓迎行事 今貂子舞踏公演『彗星』 【講演・ワークショップ】総合危機管理学会 第9回学術集会 |
| 2025年6月 | 基盤研究 教養研究講演会 no.11 オウム真理教事件を通じて現代社会を見る―「抑圧されたもの」の回帰のように みなさんmiraiプロジェクト 南三陸の森を知る講演会(福澤育林友の会主催) 【講演・ワークショップ】観想研究カンファレンス 「なる」のオートエスノグラフィー |
| 2025年7月 | 情報の教養学「慶應義塾で学ぶということ」 【講演・ワークショップ】第33回日本経営倫理学会全国研究発表大会シンポジウム:「経営倫理基準としての「利他」の可能性:東洋の経営倫理思想の系譜と稲盛和夫経営哲学」 HAPP企画 日吉音楽祭2025 |
| 2025年8月 | 第14回「庄内セミナー」「「庄内に学ぶ<生命(いのち)>-死と生を繋ぐ-」」 |
| 2025年9月 | 創造力とコミュニティ研究会30「すごいぞ!シロアリのコミュニティ」 みなさんmiraiプロジェクト 南三陸の森を知る講演会(福澤育林友の会主催) |
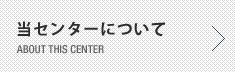



「されば賢人と愚人との別は,学ぶと学ばざるとに由って出来るものなり」
福澤諭吉『学問のすゝめ』初編
慶應義塾大学教養研究センターのミッション- (1)「教養」を定義するための研究を行うこと。
- (2)「教養」を学ぶための教育を実践すること。
- (3)教養研究と教養教育を実現するための方法を探求すること。